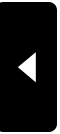かまど金
子供の教育の現場が変わりつつある。
急に変わったわけではないが、
ゆとり教育の制度がやっと身を結び始めたのではないだろうか?
総合学習とよばれ、
自ら学び、自ら考え、解決する力や、学び方、ものの考え方などを身につけさせる
という考えのもと、
色々な体験型学習を経験させる教科が増えたのは記憶に新しいが、
実際のところうまく機能していたかどうかは疑問であった。
それは何故なのだろう?
何かをする際、画期的な制度を打ち上げる事は必要だが、
それには理想とする目標に対して、
確実な手法、バイアス、指導などいくつかの条件が整ってこそ、
そうして、実際に現場で行われた事に対して、
冷静にかつ客観的に評価検証を行い、
計画の練り直しや、補正を行う事で成果が大きなものとなるのではないだろうか?
形だけにとらわれて、中身の無いシステムを作り上げてしまうと、
その理想とする目標が形骸化され、成果も見えないものとなっている。
京都市で近年行われてきた手法は、
その検証システムとして、「学校評価システム」と「教員評価システム」を取り入れている。
それが、プラスのモチベーションを作り上げてきたのではないか?
随分前になるが、大学の頃とある京都の公立高校を拝見した事があるが、
正直に申し上げて当時の公立高校は生徒も教員も目に余るものがあった。
現状に甘んじてなんら革新的な行動は無かったように見える。
「堀川の奇跡」と呼ばれる堀川高校の高校改革のパイロット校としての位置づけは、
当時、その卒業生と交流した経験からすれば、なんら不思議ではない。
すごく変わったとか言うが、当時からあの高校、そしてあの地域には独自性が見られた。
生徒もそして卒業生も母校を誇りに芸術性など精神面での強みが見られたと思う。
そんな素地から、生まれ変わった堀川高校に期待してしまうのは贔屓目かも知れない。
又、西京高校も革新が行われた学校であるが、
この二つの学校の特徴は、
最も多感な時期に現在の日本人が教育にて身に着けてこなかった・・・
欧米の教育に見られる論理性やディベート力に代表される表現を磨く事。
そして、自分の目的意識を啓発する事であろう。
とある本で読んだが、この考えは受験進学校で有名だった灘高校にも見られるような気がする。
すべてに自主性を伸ばす工夫があったようである。
時代が動き、こうした教育制度の改革によって、
次世代の人的資産が育ってゆく事は日本にとって非常に有意義な事である。
学びの場は学校に限らず、社会に出てもあるのだが、
その手法を習得する事はなかなか試練を強いられる。
より良い未来の為に、有望な次世代を作ろうとしているこれらの学校を応援したい。
京都の教育制度の改革のベースには、
かまど金の精神があるという。
子供のあるなしにかかわらず、かまどの数に応じて教育の為の資金を出し合うというものである。
社会の宝である子供を育てようという気持ちのあらわれである。
とかく、閉鎖的社会と思われる京都であるが、
こうした素敵な制度や精神はどんどん広げていただきたい。
どの分野、世界でも水平思考は可能であり、
それを実現する事が重要である。
プロなら、現状はとか言い訳を考えるのではなく、
どうすれば?あるいは何故なのか?を常に問いかけ、
顧客が満足のゆく成果を作り出す事が必要ではないだろうか?
急に変わったわけではないが、
ゆとり教育の制度がやっと身を結び始めたのではないだろうか?
総合学習とよばれ、
自ら学び、自ら考え、解決する力や、学び方、ものの考え方などを身につけさせる
という考えのもと、
色々な体験型学習を経験させる教科が増えたのは記憶に新しいが、
実際のところうまく機能していたかどうかは疑問であった。
それは何故なのだろう?
何かをする際、画期的な制度を打ち上げる事は必要だが、
それには理想とする目標に対して、
確実な手法、バイアス、指導などいくつかの条件が整ってこそ、
そうして、実際に現場で行われた事に対して、
冷静にかつ客観的に評価検証を行い、
計画の練り直しや、補正を行う事で成果が大きなものとなるのではないだろうか?
形だけにとらわれて、中身の無いシステムを作り上げてしまうと、
その理想とする目標が形骸化され、成果も見えないものとなっている。
京都市で近年行われてきた手法は、
その検証システムとして、「学校評価システム」と「教員評価システム」を取り入れている。
それが、プラスのモチベーションを作り上げてきたのではないか?
随分前になるが、大学の頃とある京都の公立高校を拝見した事があるが、
正直に申し上げて当時の公立高校は生徒も教員も目に余るものがあった。
現状に甘んじてなんら革新的な行動は無かったように見える。
「堀川の奇跡」と呼ばれる堀川高校の高校改革のパイロット校としての位置づけは、
当時、その卒業生と交流した経験からすれば、なんら不思議ではない。
すごく変わったとか言うが、当時からあの高校、そしてあの地域には独自性が見られた。
生徒もそして卒業生も母校を誇りに芸術性など精神面での強みが見られたと思う。
そんな素地から、生まれ変わった堀川高校に期待してしまうのは贔屓目かも知れない。
又、西京高校も革新が行われた学校であるが、
この二つの学校の特徴は、
最も多感な時期に現在の日本人が教育にて身に着けてこなかった・・・
欧米の教育に見られる論理性やディベート力に代表される表現を磨く事。
そして、自分の目的意識を啓発する事であろう。
とある本で読んだが、この考えは受験進学校で有名だった灘高校にも見られるような気がする。
すべてに自主性を伸ばす工夫があったようである。
時代が動き、こうした教育制度の改革によって、
次世代の人的資産が育ってゆく事は日本にとって非常に有意義な事である。
学びの場は学校に限らず、社会に出てもあるのだが、
その手法を習得する事はなかなか試練を強いられる。
より良い未来の為に、有望な次世代を作ろうとしているこれらの学校を応援したい。
京都の教育制度の改革のベースには、
かまど金の精神があるという。
子供のあるなしにかかわらず、かまどの数に応じて教育の為の資金を出し合うというものである。
社会の宝である子供を育てようという気持ちのあらわれである。
とかく、閉鎖的社会と思われる京都であるが、
こうした素敵な制度や精神はどんどん広げていただきたい。
どの分野、世界でも水平思考は可能であり、
それを実現する事が重要である。
プロなら、現状はとか言い訳を考えるのではなく、
どうすれば?あるいは何故なのか?を常に問いかけ、
顧客が満足のゆく成果を作り出す事が必要ではないだろうか?