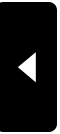新聞を斬る?
社会人の基本といわれる新聞からの情報収集ですが、
重要とは言え、必要以上に時間を掛けてはその時間が無駄ですね。
多少達人の技から盗んでみました。
テレ朝で朝の新聞チェックの番組をされていたプロデューサ(当時)のテクは、
との事である。
何しろスポーツ紙はスポーツがらみがメインなので、
社会面や経済、政治面は要約しか載せられていない。
その後、一般紙を2種類読み偏り感を排除するとの事。
確かに、近頃社説をWEBでチェックしてみると・・
記事内容によってかなり偏りが見られる点がある。
しかしながら、この一般紙の見方にもかなり効率化が図られている。
とのことである。
いわゆるレバレッジが掛けられた状態で新聞を読まれているわけである。
これを書かれていたのは、テレビ朝日の田中 義樹さんであるが、
目的をはっきりと持って読むことで、速読よりは多読の感がある読み方である。
新聞の効率的情報収集の流れ
以上のような方法である。
ここで2紙の組み合わせは、
保守的な論調の新聞と革新的な論調の新聞
「スポーツニッポン、朝日新聞、産経新聞」が典型的な組み合わせである。
以上はテレビ的な考えで新聞からの情報であるが、
新聞の論説委員をされていた方の考え方はどうであろうか?
既に出版されてかなり経過してはいるが、
轡田隆史さんの「考える力」をつける本によると・・・
とおっしゃっている。
確かにこれは納得である。
現在は重要性はわかっているが、
コストとの兼ね合いで多数の実際の新聞を読みきれない。
社会の流れを確認する意味で、WEBから社説やコラムを落として読む。
これが、先に書いたとおり新聞社の傾向がかなり出ていて面白い。
それを自分で読解して理解、納得する事で、いろんなことがわかるし、
考える練習になる。
たとえば、先のNOVAの破綻に付いては、
読売と日経でかなり糾弾先やその度合いが異なる。
そうした情報を的確に取捨選択して、客観的に見れるように鍛えて行きたい。
重要とは言え、必要以上に時間を掛けてはその時間が無駄ですね。
多少達人の技から盗んでみました。
テレ朝で朝の新聞チェックの番組をされていたプロデューサ(当時)のテクは、
まずスポーツ紙の社会面から読むのが効率的だ
との事である。
何しろスポーツ紙はスポーツがらみがメインなので、
社会面や経済、政治面は要約しか載せられていない。
その後、一般紙を2種類読み偏り感を排除するとの事。
確かに、近頃社説をWEBでチェックしてみると・・
記事内容によってかなり偏りが見られる点がある。
しかしながら、この一般紙の見方にもかなり効率化が図られている。
新聞記事は、大事な結論を先に、細かい補足説明を後に書く逆三角形構造になっている。
そのため、見出しとリード(要約文)を読めば、大体のところが分かる。
とのことである。
いわゆるレバレッジが掛けられた状態で新聞を読まれているわけである。
これを書かれていたのは、テレビ朝日の田中 義樹さんであるが、
目的をはっきりと持って読むことで、速読よりは多読の感がある読み方である。
新聞の効率的情報収集の流れ
【1】 スポーツ紙の社会面(経済面・政治面)からスタート
大きなニュースのアタリをつける。
↓
【2】 一般紙の1面へ
2紙の共通大見出しの洗い出し
↓
【3】 一般紙の社会面(経済・政治)へ
一般紙2紙に大きな見出しで載っているニュースは要チェック。
また、小さな記事でも、見出しが面白い記事は、中身も面白いケースが多い。
↓
【4】 一般紙の2面、3面…
続いて2面、3面を開く。さらに4面、5面とめくっていく。
↓
【5】 スポーツ紙に戻る
スポーツ、芸能ニュースの見出しをチェック。
営業の仕事をしている人の場合、顧客との会話のネタとして、
スポーツや芸能関係のニュースを仕入れておくとよいこともある。
以上のような方法である。
ここで2紙の組み合わせは、
保守的な論調の新聞と革新的な論調の新聞
「スポーツニッポン、朝日新聞、産経新聞」が典型的な組み合わせである。
以上はテレビ的な考えで新聞からの情報であるが、
新聞の論説委員をされていた方の考え方はどうであろうか?
既に出版されてかなり経過してはいるが、
轡田隆史さんの「考える力」をつける本によると・・・
新聞は、一面のコラム(天声人語など)から読め。
・・・一面のコラムにはエキスがつまっているからだ。
「社説」をもっと気軽に利用してもらいたい。
論を述べるだけでなく、
論の前提としてのニュースに付いても手際よく要約し解説してある・・
とおっしゃっている。
確かにこれは納得である。
現在は重要性はわかっているが、
コストとの兼ね合いで多数の実際の新聞を読みきれない。
社会の流れを確認する意味で、WEBから社説やコラムを落として読む。
これが、先に書いたとおり新聞社の傾向がかなり出ていて面白い。
それを自分で読解して理解、納得する事で、いろんなことがわかるし、
考える練習になる。
たとえば、先のNOVAの破綻に付いては、
読売と日経でかなり糾弾先やその度合いが異なる。
そうした情報を的確に取捨選択して、客観的に見れるように鍛えて行きたい。