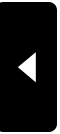金曜日その2
さて、その後は
強みを活かす話でしたが、
テキスト上から、
自社の強みとして、
人・物・金(情報)
との事でした。
人材・商品(サービス・財産)・資金(情報資源)ですね。
戦略を再構築
①ビジョンを再確認
②環境を知る
③事業を再構築
④計画・実行する ~計画立案→シュミレーション→実行
となっておりました。
この項目に付いては、③のみの実例を挙げていただき、
和菓子屋さんの糖尿病患者への新商品開発を医療機関とコラボした話が出ました。
又、他にも数点例を挙げていただきましたが、
現在考えている水平思考をこれに活かせば良いのですね。
変化ではなく、クリエイティブだけでもなく、
水平思考に因るイノベーションを進めるのが一番のようですね。
そのためには、自己資産の完全な洗い出し、
周辺環境の洗い出しに因るビジネスチャンスを見ておく、
そうして、勿論①が一番重要ですね。
どんなにいいアイデアでもそこにビジョンと食い違いがあれば、
先にすすみにくいし、売る理由が無いですね。
そして、PDCAによる④のサイクルの実現が重要と思われます。
次に、強みの見つけ方ですが、
①魅力的な事業をしている。
A今後、顧客が増えそう(なくならない)
B競争相手が少ない
C相場変動などのリスクが少ない
とのことで、
Aに付いて、衣食住は0にはならないから良いとのことですが、
果たしてどうでしょう?
確かに0にはなってませんが、少しは住居の需要というか生産量は減少してますね。
しかも・・・、作っているから自然に売れるほど儲かってはいない。
だから、先のブログにあげたような平成建設のような取り組みが素晴らしいのですよね。
いわば、業界の常識をやぶり差異性を打ち出した方式であり、
ビジョンから営業状態までが一貫しています。
そこまでして、初めて強みとなるのではないでしょうか?
何も日本一ってほどが強みではないですよね?
佐藤先生がおっしゃっているように、
この地域では一番だ!といえるようなものが強みですね。
Bについては、性別を例に挙げてられました。
でもそれだけでは?国籍が違うぐらいの差別化ほどでは。。。
そこから初めて・・・もう二ひねりぐらい必要といえます。
その差異性に基づいて、お客様が何を求めてきているのか?
そうしてどうすればもっと共感が得られるのか?を常に考える必要がありそうです。
Cの相場変動ですが、実際のところどうなのでしょう?
たとえば、Bの競争相手が少ない状況ならば、
相場変動に因る原材料は価格に上乗せしているだけのところもありますね。
②優位に立てる技がある
ア 商品・サービス、技術に特徴がある
イ 他者が出来ない方法でコストを抑えられる
ウ 営業・広告宣伝に特徴がある
とのことです。
アの一つは特許などですね。また、自己開発技術は特徴となりますね。
イはまさに、先に述べた平成建設が行っているワザですね。
ただ、そのコストの削減はフェアーなもので、しかも人材である社員に還元されたり、
あるいはお客様に還元されるようなものであるべきと思います。
ウについては、まさに今回の方の専門ですね。
ただ、この手法に付いては、
マーケティングミックスをうまくフィットさせる方向がベストではないでしょうか?
ブランディングを進めていけば、
自然にこの分野は出来てくるような気がします。
次に自社の経営資源をたな卸しとの事でした。
遠慮せずになんでも挙げていくとのことで、
ある方がある特定の分野で3種ぐらいの免許をもたれていて、
その分野が経営状況が苦しいのでやめるとの事でした。
他にも多数免許をお持ちで、いろんなことが考えられますが、
そこでビジョンが何かをお聞きしたいと思いました。
そのビジョンが、今までやってきた分野に最も適したものなら、
苦しい状況でもそこに活路があるような気がします。
その分野での経験もあり、熱意もあるのなら可能性をすぐに捨てるのは早いですね。
その後、まったく違う分野の多角化の例を出され、
技術が導入できるのなら、まったく違う分野も大丈夫との事でした。
そこにしっかりした理念があれば?の話だとは思いますが。
その後、フレームワークに至り、
ご存知SWOTが出てまいりました。
中小の場合はSだけ特に考えて、
残りの三つはそれだけでカバーしきるとのお話で、
そういった考えもあるのだなと拝聴しました。
私自身は、SWOTについての現在の理解は、
S・W・O・Tのすべてに付いて、
出来る限りMECEで列挙して、
その中でクロスを掛けることで次のステップを考えるものと理解してます。
Wを知らなければ、いつまでたっても自己及び自社理解がすすみませんし、
次にやっておく事を先延ばしになってしまいますね。
Oについては、チャンスだからといって安易にやっても、
その裏のTが裏にあることの理解のが必要だと思います。
Tを理解する事は、避けられない状況をいかに回避するか?
或いは、どう対処するかの方法であり、
イノベーションシンキングにても、常に考えられる事を考えておけば、
競合他社の手も予測できるとの事です。
最後は強みを活かすアイデアの作り方とのことで、
アイデアは数多く考える、たくさんメモする、ポストイットに書き出すとのお話を頂きました。
ただ、ポストイットに書き出すだけでは思考の広がりは得にくいのではないでしょうか?
moreメソッドのような方法をとるか?
或いは、まったく違う概念なども踏まえて、
マインドマップなどに応用すれば、画期的に考えがうかんでくるはずです。
その他、テキスト上ではゼロベース思考で考えるとの表現がありました。
既成概念や常識をいったん忘れて発案するとの例があり、
「若い女性向け」→「男性対象にしたら?」
「店で売るのが常識」→「定期的に届けに行ったら?」
「仕入れ販売があたりまえ」→「自社で作ったら?」
「当社では経験がない・・」→「経験者の手を借りたら?」
との例がありました。
どこかで・・・って思い、
良く考えると、これは単に「ルールを破れ」という水平思考用のゲームパターンですね。
実際のゼロベースとはそんなに底の薄いものでしょうか?
定義の中に含まれる前提を疑うような、
或いは経験と既知の事実からの推測を覆すような、
あるいはゲームのルールさえも変えてしまうようなことを意味するはずです。
実体験から考えるとの例もありました。
ここはさらりと流されたのですが、
じつはここに大きな意味がありますね。
お客様の立場で感じた事や実体験をもとにアイデアをだす。
と書かれてあり、お客様の立場に立つことは基本ですね。
自分が体験してはっきり理解すべきところだと思います。
又、実体験ですが、すべての人がアイデアが出るような実体験を得るものでしょうか?
常日頃考えつつけていることで、いろんなことがカラー効果により見えてくると思います。
まったく違う業種を見る事も必要でしょうし、そこにヒントが隠れている事もあります。
又、本を読み感じる事で経験に類似した情報も得られますし、
そこから自分自身が考えをさらに深める事も出来ますね。
テキスト上、もうすこしありましたが、
講義はこれまででした。
テキストを見ると大体の流れは判りますが、
いつかこのことに付いては書こうと思います。
現在、マーケティングミックスやフィットなどについて考えてますが、
いかにMECEかが重要だというのが理解できて来た様な気がします。
すべてを組み合わせて、自分の世界観が創出できるように何とかしたいですね。
強みを活かす話でしたが、
テキスト上から、
自社の強みとして、
人・物・金(情報)
との事でした。
人材・商品(サービス・財産)・資金(情報資源)ですね。
戦略を再構築
①ビジョンを再確認
②環境を知る
③事業を再構築
④計画・実行する ~計画立案→シュミレーション→実行
となっておりました。
この項目に付いては、③のみの実例を挙げていただき、
和菓子屋さんの糖尿病患者への新商品開発を医療機関とコラボした話が出ました。
又、他にも数点例を挙げていただきましたが、
現在考えている水平思考をこれに活かせば良いのですね。
変化ではなく、クリエイティブだけでもなく、
水平思考に因るイノベーションを進めるのが一番のようですね。
そのためには、自己資産の完全な洗い出し、
周辺環境の洗い出しに因るビジネスチャンスを見ておく、
そうして、勿論①が一番重要ですね。
どんなにいいアイデアでもそこにビジョンと食い違いがあれば、
先にすすみにくいし、売る理由が無いですね。
そして、PDCAによる④のサイクルの実現が重要と思われます。
次に、強みの見つけ方ですが、
①魅力的な事業をしている。
A今後、顧客が増えそう(なくならない)
B競争相手が少ない
C相場変動などのリスクが少ない
とのことで、
Aに付いて、衣食住は0にはならないから良いとのことですが、
果たしてどうでしょう?
確かに0にはなってませんが、少しは住居の需要というか生産量は減少してますね。
しかも・・・、作っているから自然に売れるほど儲かってはいない。
だから、先のブログにあげたような平成建設のような取り組みが素晴らしいのですよね。
いわば、業界の常識をやぶり差異性を打ち出した方式であり、
ビジョンから営業状態までが一貫しています。
そこまでして、初めて強みとなるのではないでしょうか?
何も日本一ってほどが強みではないですよね?
佐藤先生がおっしゃっているように、
この地域では一番だ!といえるようなものが強みですね。
Bについては、性別を例に挙げてられました。
でもそれだけでは?国籍が違うぐらいの差別化ほどでは。。。
そこから初めて・・・もう二ひねりぐらい必要といえます。
その差異性に基づいて、お客様が何を求めてきているのか?
そうしてどうすればもっと共感が得られるのか?を常に考える必要がありそうです。
Cの相場変動ですが、実際のところどうなのでしょう?
たとえば、Bの競争相手が少ない状況ならば、
相場変動に因る原材料は価格に上乗せしているだけのところもありますね。
②優位に立てる技がある
ア 商品・サービス、技術に特徴がある
イ 他者が出来ない方法でコストを抑えられる
ウ 営業・広告宣伝に特徴がある
とのことです。
アの一つは特許などですね。また、自己開発技術は特徴となりますね。
イはまさに、先に述べた平成建設が行っているワザですね。
ただ、そのコストの削減はフェアーなもので、しかも人材である社員に還元されたり、
あるいはお客様に還元されるようなものであるべきと思います。
ウについては、まさに今回の方の専門ですね。
ただ、この手法に付いては、
マーケティングミックスをうまくフィットさせる方向がベストではないでしょうか?
ブランディングを進めていけば、
自然にこの分野は出来てくるような気がします。
次に自社の経営資源をたな卸しとの事でした。
遠慮せずになんでも挙げていくとのことで、
ある方がある特定の分野で3種ぐらいの免許をもたれていて、
その分野が経営状況が苦しいのでやめるとの事でした。
他にも多数免許をお持ちで、いろんなことが考えられますが、
そこでビジョンが何かをお聞きしたいと思いました。
そのビジョンが、今までやってきた分野に最も適したものなら、
苦しい状況でもそこに活路があるような気がします。
その分野での経験もあり、熱意もあるのなら可能性をすぐに捨てるのは早いですね。
その後、まったく違う分野の多角化の例を出され、
技術が導入できるのなら、まったく違う分野も大丈夫との事でした。
そこにしっかりした理念があれば?の話だとは思いますが。
その後、フレームワークに至り、
ご存知SWOTが出てまいりました。
中小の場合はSだけ特に考えて、
残りの三つはそれだけでカバーしきるとのお話で、
そういった考えもあるのだなと拝聴しました。
私自身は、SWOTについての現在の理解は、
S・W・O・Tのすべてに付いて、
出来る限りMECEで列挙して、
その中でクロスを掛けることで次のステップを考えるものと理解してます。
Wを知らなければ、いつまでたっても自己及び自社理解がすすみませんし、
次にやっておく事を先延ばしになってしまいますね。
Oについては、チャンスだからといって安易にやっても、
その裏のTが裏にあることの理解のが必要だと思います。
Tを理解する事は、避けられない状況をいかに回避するか?
或いは、どう対処するかの方法であり、
イノベーションシンキングにても、常に考えられる事を考えておけば、
競合他社の手も予測できるとの事です。
最後は強みを活かすアイデアの作り方とのことで、
アイデアは数多く考える、たくさんメモする、ポストイットに書き出すとのお話を頂きました。
ただ、ポストイットに書き出すだけでは思考の広がりは得にくいのではないでしょうか?
moreメソッドのような方法をとるか?
或いは、まったく違う概念なども踏まえて、
マインドマップなどに応用すれば、画期的に考えがうかんでくるはずです。
その他、テキスト上ではゼロベース思考で考えるとの表現がありました。
既成概念や常識をいったん忘れて発案するとの例があり、
「若い女性向け」→「男性対象にしたら?」
「店で売るのが常識」→「定期的に届けに行ったら?」
「仕入れ販売があたりまえ」→「自社で作ったら?」
「当社では経験がない・・」→「経験者の手を借りたら?」
との例がありました。
どこかで・・・って思い、
良く考えると、これは単に「ルールを破れ」という水平思考用のゲームパターンですね。
実際のゼロベースとはそんなに底の薄いものでしょうか?
定義の中に含まれる前提を疑うような、
或いは経験と既知の事実からの推測を覆すような、
あるいはゲームのルールさえも変えてしまうようなことを意味するはずです。
実体験から考えるとの例もありました。
ここはさらりと流されたのですが、
じつはここに大きな意味がありますね。
お客様の立場で感じた事や実体験をもとにアイデアをだす。
と書かれてあり、お客様の立場に立つことは基本ですね。
自分が体験してはっきり理解すべきところだと思います。
又、実体験ですが、すべての人がアイデアが出るような実体験を得るものでしょうか?
常日頃考えつつけていることで、いろんなことがカラー効果により見えてくると思います。
まったく違う業種を見る事も必要でしょうし、そこにヒントが隠れている事もあります。
又、本を読み感じる事で経験に類似した情報も得られますし、
そこから自分自身が考えをさらに深める事も出来ますね。
テキスト上、もうすこしありましたが、
講義はこれまででした。
テキストを見ると大体の流れは判りますが、
いつかこのことに付いては書こうと思います。
現在、マーケティングミックスやフィットなどについて考えてますが、
いかにMECEかが重要だというのが理解できて来た様な気がします。
すべてを組み合わせて、自分の世界観が創出できるように何とかしたいですね。